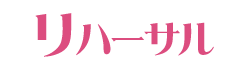 |
「お前の姉ちゃん、すごいよな」
ネットの向こう側から聞こえてきた小さな声に、月島紅葉は足を止めた。
東雄平はバッターボックスに立っていたが、一通り打ち終わったのか、こちらに顔を向けている。
「そりゃぁ、小学生の頃から男子に混じって投げてたもん」
てっきり青葉のことだと思って答えると、東は少し口ごもった。
「いや、そっちの月島じゃなくて」
相変わらず無表情に近いが、珍しく視線が揺れている。
紅葉は、小首を傾げた。
「一葉お姉ちゃんの方?」
東は無言で頷くと、入り口の前に立てかけていた鞄を掴肩に掛け、金網の扉を開けた。紅葉が立っているベンチに腰掛け、手にしたバットを鞄に仕舞い始める。
一葉は、紅葉が物心ついた頃には既に、母親代わりとして家の一切のことを切り盛りしていた。だから紅葉や青葉にとっては間違いなく「凄い姉」なのだが、喫茶店でしか会うことがない東が、どうして一葉に感心するのだろうか。一葉と結婚前提にまでこぎ着けた兄から何か聞いたのかと思って紅葉が尋ね返すと、東はボソボソと喋り始めた。
「単にからかっているようで、スゲー考えてるよな」
「例えば?」
「俺たちが甲子園に行ったら結婚するって約束してただろ」
「あー、してたね」
東の兄、純平の一目惚れという形で二人の交際は始まっていたが、順調に進展していたようで、ついにプロポーズにまでこぎ着けていたらしい。
それが確か、夏前だっただろうか。
ところがその返事は一時保留されたらしく、暫くして出された答えが「星秀が甲子園出場を決めたら」だった。
「アレ、俺と一緒に、兄ちゃんにまた野球させる為じゃなかったのか?」
自問自答するような東の言葉に、紅葉は天井を見上げた。
「あー、言われてみれば?」
そんな気がしなくもないと、紅葉は頷いた。
一葉の返事を聞いた純平は、必死な形相で星秀の練習に顔を出すようになったらしい。そして監督が高齢でノック練習などが辛いことから、元甲子園球児の知識と技術をかわれて、臨時コーチとして練習に参加するようになった。おかげで紅葉のいる中等部でも「放課後になると高等部から奇妙な叫び声が聞こえる」「野球部の練習時のかけ声が変」と、話題になっていた。
けれど実際、純平の指導で星秀ナインの技術は格段に上がったらしい。甲子園では後から合流して、試合前に泊まり込みで練習に参加することになっている。
これらの事は両親の理解と協力が大きいが、きっかけを作ったのは一葉で間違いない。
「兄ちゃんと一緒に甲子園に行けるんだ」
嬉しそうに口元を緩める東に、紅葉はなんだか嬉しくなった。
青葉は男子と一緒に野球をして、男子顔負けのピッチングをするから、色々な人から「凄い」とよく言われる。けれど一葉に関しては「偉いね」という評判ばかりなのだ。
ましてや、野球しか目に入っていない東に「凄い」と高く評価された。それがなによりも誇らしく感じられた。
そう、一葉は凄い。青葉みたいに目立つことはないが、凄い姉なのだ。
「でもまぁ、遊ばれていたのは間違いないと思うよ」
茶化すように、紅葉は唇を開いた。
「兄ちゃんも、気付いても良さそうなのにな」
甲子園に行けたら、という条件だったにも関わらず、ちゃんとお互いの両親に紹介しているのだ。万が一甲子園行きがパーになったとしても、日取りが変わるだけで「結婚する」という事実は変わりなかっただろう。
「え、全然?」
東の言葉に、紅葉が呆れたように口を開けた。
「兄ちゃんは、何だかんだで一直線なところがあるからな……」
東は小さくため息を吐いているが、目元はかすかに笑っている。そしてゆっくりと立ち上がると、道具を仕舞ったバックを背負った。
「明日出発するんだっけ?」
バッティングセンターの出入り口に向かう東のすぐ後を、紅葉がトコトコとついていく。
東たちは、明日甲子園に向かって出発する事になっていた。そして宿泊先で練習を重ね、数日後には開会式を迎える。
「帰ってきたら結婚式だね」
「まずは甲子園で一勝だろ」
声を弾ます紅葉に、東は呆れたような口調で返した。
「だって、ワカちゃんの夢ってさ、どう見ても決勝戦じゃない?」
光がピッチャーで、舞台は超満員の甲子園。
若葉が最後に見た夢の話は、紅葉も朝食の席で聞いていたし、青葉や光が、口癖のように何度も呟いているのを聞いている。
「ゆーへーと光がいるもん、大丈夫だよ」
紅葉が自信満々に告げると、東は肩越しに振り返って、「まぁな」と唇の端を持ち上げた。
「今からお義姉さんって呼ぶ練習でもしとく?」
「お前がお義兄ちゃんって呼ぶならな」
素っ気ない東の言葉に、紅葉は小走りになって東の正面へと回った。そして満面の笑みを浮かべ
て、怪訝そうな表情の東を見据えた。
「ゆーへーお兄ちゃん」
普段と全く違う甘ったるい声と共に、小首を傾げてみせる。
「どう?」
したり顔に変わった紅葉に、東は深く眉を寄せた。
「気持ち悪りぃな……」
「失敬だなァ」
東の感想に、紅葉は唇を尖らせた。そして入り口の扉を身体で押しあけようとすると、東がすっと腕を伸ばし、押し開けた。見上げると、無言で先に行くよう促している。
紅葉は礼を言いながら先に扉をくぐり、カウンターに向かった。
そこでは青葉がパイプ椅子に腰掛け、店番をしている。
青葉は、後から出てきた東と紅葉の顔を見比べて目を丸くすると、紅葉に視線を戻した。
「明日の準備があるんだから、邪魔しちゃダメよ?」
紅葉は「わかってるもーん」と返しながら、手にしていた段ボールをカウンターの上に載せていると、東が口を開いた。
「そういう月島は終わったのか?」
「ええ、まぁ。大体」
そう返す青葉の目が泳いでいる。おそらくまだ準備が終わっていないのだろう。
「そういやさっき、入り口で紅葉が何かやってたみたいですけど」
「あぁ……」
青葉の言葉に、東は僅かに両眉を寄せた。東にしては珍しく、困ったような、それでいて呆れているかのような表情を浮かべている。
「弟と妹になる練習をしてたの」
そう答え、紅葉がカウンターに両肘を突いて青葉を見上げると、青葉はさらに怪訝な表情を浮かべた。
<了>
ネットの向こう側から聞こえてきた小さな声に、月島紅葉は足を止めた。
東雄平はバッターボックスに立っていたが、一通り打ち終わったのか、こちらに顔を向けている。
「そりゃぁ、小学生の頃から男子に混じって投げてたもん」
てっきり青葉のことだと思って答えると、東は少し口ごもった。
「いや、そっちの月島じゃなくて」
相変わらず無表情に近いが、珍しく視線が揺れている。
紅葉は、小首を傾げた。
「一葉お姉ちゃんの方?」
東は無言で頷くと、入り口の前に立てかけていた鞄を掴肩に掛け、金網の扉を開けた。紅葉が立っているベンチに腰掛け、手にしたバットを鞄に仕舞い始める。
一葉は、紅葉が物心ついた頃には既に、母親代わりとして家の一切のことを切り盛りしていた。だから紅葉や青葉にとっては間違いなく「凄い姉」なのだが、喫茶店でしか会うことがない東が、どうして一葉に感心するのだろうか。一葉と結婚前提にまでこぎ着けた兄から何か聞いたのかと思って紅葉が尋ね返すと、東はボソボソと喋り始めた。
「単にからかっているようで、スゲー考えてるよな」
「例えば?」
「俺たちが甲子園に行ったら結婚するって約束してただろ」
「あー、してたね」
東の兄、純平の一目惚れという形で二人の交際は始まっていたが、順調に進展していたようで、ついにプロポーズにまでこぎ着けていたらしい。
それが確か、夏前だっただろうか。
ところがその返事は一時保留されたらしく、暫くして出された答えが「星秀が甲子園出場を決めたら」だった。
「アレ、俺と一緒に、兄ちゃんにまた野球させる為じゃなかったのか?」
自問自答するような東の言葉に、紅葉は天井を見上げた。
「あー、言われてみれば?」
そんな気がしなくもないと、紅葉は頷いた。
一葉の返事を聞いた純平は、必死な形相で星秀の練習に顔を出すようになったらしい。そして監督が高齢でノック練習などが辛いことから、元甲子園球児の知識と技術をかわれて、臨時コーチとして練習に参加するようになった。おかげで紅葉のいる中等部でも「放課後になると高等部から奇妙な叫び声が聞こえる」「野球部の練習時のかけ声が変」と、話題になっていた。
けれど実際、純平の指導で星秀ナインの技術は格段に上がったらしい。甲子園では後から合流して、試合前に泊まり込みで練習に参加することになっている。
これらの事は両親の理解と協力が大きいが、きっかけを作ったのは一葉で間違いない。
「兄ちゃんと一緒に甲子園に行けるんだ」
嬉しそうに口元を緩める東に、紅葉はなんだか嬉しくなった。
青葉は男子と一緒に野球をして、男子顔負けのピッチングをするから、色々な人から「凄い」とよく言われる。けれど一葉に関しては「偉いね」という評判ばかりなのだ。
ましてや、野球しか目に入っていない東に「凄い」と高く評価された。それがなによりも誇らしく感じられた。
そう、一葉は凄い。青葉みたいに目立つことはないが、凄い姉なのだ。
「でもまぁ、遊ばれていたのは間違いないと思うよ」
茶化すように、紅葉は唇を開いた。
「兄ちゃんも、気付いても良さそうなのにな」
甲子園に行けたら、という条件だったにも関わらず、ちゃんとお互いの両親に紹介しているのだ。万が一甲子園行きがパーになったとしても、日取りが変わるだけで「結婚する」という事実は変わりなかっただろう。
「え、全然?」
東の言葉に、紅葉が呆れたように口を開けた。
「兄ちゃんは、何だかんだで一直線なところがあるからな……」
東は小さくため息を吐いているが、目元はかすかに笑っている。そしてゆっくりと立ち上がると、道具を仕舞ったバックを背負った。
「明日出発するんだっけ?」
バッティングセンターの出入り口に向かう東のすぐ後を、紅葉がトコトコとついていく。
東たちは、明日甲子園に向かって出発する事になっていた。そして宿泊先で練習を重ね、数日後には開会式を迎える。
「帰ってきたら結婚式だね」
「まずは甲子園で一勝だろ」
声を弾ます紅葉に、東は呆れたような口調で返した。
「だって、ワカちゃんの夢ってさ、どう見ても決勝戦じゃない?」
光がピッチャーで、舞台は超満員の甲子園。
若葉が最後に見た夢の話は、紅葉も朝食の席で聞いていたし、青葉や光が、口癖のように何度も呟いているのを聞いている。
「ゆーへーと光がいるもん、大丈夫だよ」
紅葉が自信満々に告げると、東は肩越しに振り返って、「まぁな」と唇の端を持ち上げた。
「今からお義姉さんって呼ぶ練習でもしとく?」
「お前がお義兄ちゃんって呼ぶならな」
素っ気ない東の言葉に、紅葉は小走りになって東の正面へと回った。そして満面の笑みを浮かべ
て、怪訝そうな表情の東を見据えた。
「ゆーへーお兄ちゃん」
普段と全く違う甘ったるい声と共に、小首を傾げてみせる。
「どう?」
したり顔に変わった紅葉に、東は深く眉を寄せた。
「気持ち悪りぃな……」
「失敬だなァ」
東の感想に、紅葉は唇を尖らせた。そして入り口の扉を身体で押しあけようとすると、東がすっと腕を伸ばし、押し開けた。見上げると、無言で先に行くよう促している。
紅葉は礼を言いながら先に扉をくぐり、カウンターに向かった。
そこでは青葉がパイプ椅子に腰掛け、店番をしている。
青葉は、後から出てきた東と紅葉の顔を見比べて目を丸くすると、紅葉に視線を戻した。
「明日の準備があるんだから、邪魔しちゃダメよ?」
紅葉は「わかってるもーん」と返しながら、手にしていた段ボールをカウンターの上に載せていると、東が口を開いた。
「そういう月島は終わったのか?」
「ええ、まぁ。大体」
そう返す青葉の目が泳いでいる。おそらくまだ準備が終わっていないのだろう。
「そういやさっき、入り口で紅葉が何かやってたみたいですけど」
「あぁ……」
青葉の言葉に、東は僅かに両眉を寄せた。東にしては珍しく、困ったような、それでいて呆れているかのような表情を浮かべている。
「弟と妹になる練習をしてたの」
そう答え、紅葉がカウンターに両肘を突いて青葉を見上げると、青葉はさらに怪訝な表情を浮かべた。
<了>
|
|